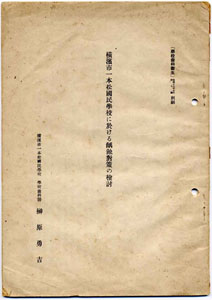HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第112号
「開港のひろば」第112号
|
展示余話
イセザキ界隈成立前史
その後学校歯科医の委嘱が進み、昭和9(1934)年には横浜市内67校のうち62校に学校歯科医が置かれるようになり、同年7月には横浜市学校歯科医会が設立された。
榊原は、昭和6(1931)年に明陽会のメンバーのなかで1人、一本松小学校の学校歯科医に残り、診療と調査を行った。そして同校で行った調査をまとめ、次々と成果を発表していった。昭和8(1933)年に発表した「精密調査に於ける齲蝕(うしょく)状況に就いて」(横浜市一本松尋常小学校[編])につづき、「横浜市一本松小学校に於ける齲蝕予防処置術式に就て」(横浜市一本松小学校[編] [1938年])、「昭和14年5月 第9回全国学校歯科医大会 横浜市一本松小学校に於けるボン式診療を応用せる歯科診療第1年の成績に就いて」(榊原勇吉著 1939年)、「横浜市一本松国民学校に於ける齲蝕対策の検討」(榊原勇吉編『学校歯科衛生』第10号所収1943年 写真4)、「本校に於ける累加的診療について」(横浜市一本松国民学校[編] 1943年)などである。なかでも『学校歯科衛生』第10号に収録された論文は、昭和13(1938)年に入学した児童から、累年的に全齲蝕の管理を実施し、昭和16年までの4年間の成果をまとめたもので、この論文は、昭和18年に開催された全国学校歯科医大会で、文部大臣賞を受賞している。なおこの時行われた調査は、論文発表後も続けられ、結果として昭和19年3月には、未処置歯を持つ児童をなくすことに成功している。榊原は、一本松小学校における検診と治療を、同年学童疎開により診療ができなくなるまで行った。
榊原が歯科医院を設けた十五銀行ビルは、戦後米軍に接収されたため、診療所の立ち退きを余儀なくされ、榊原は新たに横浜市港北区内に診療所を設け、診療を開始した。また昭和26(1951)年からは、周辺に歯科医師が不在で学校歯科医のなり手の無かった横浜市立山下小学校(横浜市緑区)の学校歯科医を引き受け、同校での仕事は、昭和53(1978)年、89歳で亡くなるまで続けられた(写真5)。
なお、榊原ほか横浜市内の学校歯科医により昭和9年に創設された横浜市学校歯科医会は、戦中の中断を経て昭和23(1948)年、再建された。榊原は再建された同会の会長となり、昭和38(1963)年まで同職を務めた。同会は、全国に先駆けて歯科衛生士の学校巡回指導を開始するなど活動を続け、平成11(1999)年、横浜市歯科医師会と合同し、閉会している。
本稿の執筆にあたり、樋口輝雄氏(ひぐち てるお 日本歯科大学新潟生命歯学部医の博物館)の御教示を得た。記して謝意を表します。
(石崎康子)