HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第108号
「開港のひろば」第108号
|
資料よもやま話1
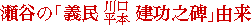
明治10(1877)年から12年にかけて、瀬谷村を中心に繰り広げられた地租改正不服運動の経過については、高崎進「瀬谷村他六ヶ村改租不服運動の展開」(『神奈川県史研究』37、昭和53年)に詳しい。運動の焦点は、収穫高や肥料代等地域の実情を勘案して村々が作成した「地位等級表」を、県側が組み直して、画一的な等級表を強制しようとしたことにあった。瀬谷村を含む鎌倉郡北部は、畑が田の約6倍にも及ぶ畑作地域で、県の「等級表」を基準にすると、4倍以上の負担増を招くこととなり、村々にとっては死活問題であった。
不服運動には、瀬谷村・二ツ橋村をはじめ、多い時で12ヶ村が参加し、訴願先を神奈川県令から地租改正事務局、さらには東京上等裁判所へと変えながら、県の等級表の不当性と、正当な地価算出を要求し、粘り強い主張を続けた。残念ながら彼等の願いは聞き届けられなかったが、隣村の仲裁により、明治12年10月不服一件の出費の償として、6000円が県から貸し出された。
これらの運動経過を示す史料としては、「仙田充治(せんだのぶじ)家文書」「露木重久(つゆきしげひさ)家文書」に、上申書や返答書の写しを綴った一件文書が残されており(一部は当館閲覧室にて公開)、『神奈川県史 資料編13』、『瀬谷区の歴史(生活史料編2)』に収録されている。
不服運動の過程では悲劇もあった。リーダー的存在であった瀬谷村戸長(こちょう)の川口儀右衛門(かわぐちぎえもん)と、村用係(むらようかかり)の平本平右衛門(ひらもとへいえもん)の二人が、途半ばにして病に倒れたのである。明治25年、二人の功績を讃えて、現在の瀬谷駅北口付近に記念碑が建立された。碑は高さ211センチ、幅86センチ、厚さ13.5センチ。正面には、![]() と刻まれ、裏面には、東京上等裁判所への訴願に加わった瀬谷・二ツ橋・和泉・汲沢・深谷の旧5ヶ村の45名が発起人として名を連ねている(下表)。
と刻まれ、裏面には、東京上等裁判所への訴願に加わった瀬谷・二ツ橋・和泉・汲沢・深谷の旧5ヶ村の45名が発起人として名を連ねている(下表)。
| 中和田村和泉 | 富士見村汲沢 | ||
|---|---|---|---|
| 鈴木市左衛門 清水源右衛門 石川孫右衛門 安西六郎兵衛 |
清水武左衛門 山村儀助 清水平四郎 入内嶋右衛門 横山杢右衛門 |
森織兵衛 石井平右衛門 石井菊右衛門 石井儀兵衛 |
石井菊次郎 高村□右衛門 石井武左衛門 森與左衛門 森清左衛門 |
| 富士見村深谷 | 瀬谷村 | ||
| 川辺治兵衛 鈴木定次郎 山田半左衛門 |
川辺兵□衛門 川辺七之助 川辺徳次郎 |
守屋平輔 仙田友吉 露木昌平 高橋兵右衛門 高橋市右衛門 相原惣八 石井弥次右衛門 仙田由兵衛 岩崎一平 川口源之蒸〔丞〕 |
佐藤徳兵衛 小島源次郎 籾山五左衛門 市川角左衛門 青木七兵衛 露木次左衛門 水村八右衛門 平本甚左衛門 露木要之助 平本七郎兵衛 小島政五郎 |
高橋一郎氏の調査をもとに作成 瀬谷村には、旧二ツ橋村を含む
昭和3(1928)年11月28日、川口・平本の五十回忌の報恩供養が瀬谷小学校校庭で行われた。地元選出代議士の川口義久(かわぐちよしひさ)(儀右衛門(ぎえもん)の息子)のほか、鈴木喜三郎(すずききさぶろう)元内相や、鎌倉郡内の町村長ら約400名が参加した(『横浜貿易新報』昭和3年11月29日)。式上、瀬谷銀行重役の小島政八(こじままさはち)が祭文を朗読した。小島の父・政五郎(まさごろう)も、川口・平本とともに不服運動を主導した一人であった。
この祭文の原本と思われる史料が、平本平右衛門(ひらもとへいえもん)のご子孫宅で大切に保管されている。昨年の「村々の文明開化」展で出陳(初公開)させて頂いたが、所蔵者の御厚意により、この場を借りて全文を紹介する。



