HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第108号
「開港のひろば」第108号
|
資料よもやま話1
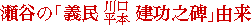
![]()
王政復古して明治の聖代となり、万政速(すみやか)に釐革(りかく)され群民歓喜感激せさるなし、偶々(たまたま)明治九年地租之制大(おおい)に変し、瀬谷二ツ橋和泉汲沢及深谷之五村貢租特に偏重ならむとす、五村之民驚心(きょうしん)駭目(がいもく)色を失ふ、当時封建之制既に滅せりと雖、因襲深く固くして遺習堅きこと猶鉄之如く、官閾(いき)徒(いたづら)に昂(たか)くして民位猥(みだり)に賤(いやし)まれ、民また退嬰自ら卑に甘(あまん)し、会々(たまたま)不平ありとも、異日禍患之及はんことを虞(おそ)れて、悚緘(しょうかん)黙認し、敢て伸展を企(くわだ)つる志なし、此時にあたり、川口平本二君のあるあり、慨然(がいぜん)として起(た)ち時艱(じなん)を匡救(きょうきゅう)せむことを志(こころざ)し、心窃(ひそか)に陳異(ちんい)を期す、敢然硬直の議を提唱し、激励儕輩(さいはい)を率ひ詳説結束を鞏(かた)くし、又挺身官に愬(うった)へ弁難陳疏頗る勉め、侃諤(かんがく)臻(いたら)らさるなく威嚇圧迫屡々(るる)加へられしも、剛強撓(たわ)まず、寸進肉迫益々努められき、当時交通之便未だ備はらず、輙(すなわ)ち就韈(しゅうべつ)して東京に往返し、時に淹留(えんりゅう)月を踰(こ)ゆることあり、以て寒暑を冒し数歳ニ及へるも倦(う)ます、夙夜(しゅくや)議を練り計を尽し、東奔(とうほん)西馳(せいし)還(ま)た家を顧るに遑(いとま)あらす、唯々反正帰平を求むるのみ、而(しこうし)て未だ得(え)す、会々(たまたま)乕疫流(これら)播(は)す、二君不幸にして此悪疫に侵され相尋(つい)て殪(たお)れぬ、実に明治十二年夏秋の候となす、今を距ること正に五十年なり、後(の)ち官我ら疾苦(しっく)を愍(なぐさ)み、金六千円を賜ひ、地租之偏重を緩和するの資と為す、蓋(けだ)し両君砕身の功に因(よ)らすむはあらさる也、是乃(すなわ)ち吾人之父祖先輩胥(みな)謀り、明治廿五年三月碑を建て高勲偉績を無窮に伝ふ、これ之を![]() となす焉、昭和三年十一月二十八日五十年祭ニあたり事蹟の湮滅せんことを恐れ、父老之讃称(さんしょう)誨示(かいじ)する所を録し、以て之が由来を明かにすと云爾(しかいう)
となす焉、昭和三年十一月二十八日五十年祭ニあたり事蹟の湮滅せんことを恐れ、父老之讃称(さんしょう)誨示(かいじ)する所を録し、以て之が由来を明かにすと云爾(しかいう)
季友小嶋政五郎(まさごろう)来助
二男 政八(まさはち)誌す
(平本忠良氏所蔵)
その後、![]() は、平成14年4月、瀬谷駅北口開発に伴い、徳善寺(とくぜんじ)境内に移設され、同年横浜市の地域文化財として指定・登録され、現在に至っている。
は、平成14年4月、瀬谷駅北口開発に伴い、徳善寺(とくぜんじ)境内に移設され、同年横浜市の地域文化財として指定・登録され、現在に至っている。
(松本洋幸)


