HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第100号
「開港のひろば」第100号
|
企画展
「開港150プレリュード ハリスと横浜」
ハリスと横浜」
遣米使節をめぐる英・米・仏の思惑
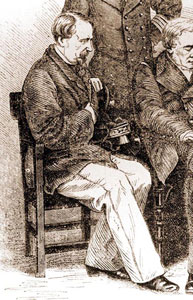
ド・ベルクールの対応
フランス総領事ド・ベルクールは、使節の出発が迫った1860年1月28日、本国外務省につぎのような報告を送った(Correspondance Politique, Japon, Vol.2, No.26)。
「1858年に調印された日米条約の批准書交換が、条約に則り、本年はじめにワシントンでおこなわれることになった。…米軍艦ポーハタンが日本使節を運ぶため間もなく江戸に到着予定である。サンフランシスコまで送り届けることになっている。今月10日に出航し、ワシントンには4月初めに到着予定である。
私は時々、機会をとらえて外国奉行らとの会談の場で、ヨーロッパへの同様の派遣、つまりパリやロンドンにも使節を派遣する可能性をそれとなく尋ねてみた。かれらの返答は、かれらの公務が江戸を離れることを許さないだろう、あるいは別の者は航海に慣れていないので、との返答だった。
イギリス公使のオールコック氏がより直截にこの問題を閣老らに問い詰めたところ、かれらの返事はただ一言、『もう少し先となるだろう』であった。日本が初めて列強の一国に派遣するこの使節の反応についてワシントンで観察することは関心を呼ぶものだろう。西欧文明と直に接したことで日本人がいだく印象がどのようなものであるか、興味ぶかいが、それとは別に、ロシアとアメリカがかれらの個別の利益と引き替えに現行条約を無効にし、日本をこの2国の庇護下におくため、江戸とペテルブルグとワシントンの政府間で何らかの合意がなされるらしいとの、ここ江戸で流れているうわさに根拠があるのか、どうかを知るよい機会となるだろう。」
ド・ベルクールとオールコックは、正確な情報がないため、使節が単にアメリカに赴くだけでなく、その後、フランスとイギリスを外して、ロシアに向かうのではないか、と危惧したのである。
また、ハリスがこの使節派遣を機に、引退を考えているらしいことも記している。
「江戸にいるアメリカ公使のハリス氏は、その思わしくない健康状態が幸いしてか、この最後の好機をとらえることができた。早期に引退することを切望しているようだ。」
フランス本省のうごき
フランス外務省は、この遣米使節に感心を寄せ、江戸駐在のド・ベルクールからの報告以外にも、ロンドンとサンクトペテルブルグ駐在外交官を使って独自に情報収集をおこなった。当時、日本からの報告はヨーロッパ本国に届くまで約2ヵ月を要した。
ロシアへの派遣について、フランス外務省はつぎのように分析していた(同前、1860年4月27日付、駐ロンドン及び駐サンクトペテルブルグ大使宛て意見書の草稿)。
「ロシアに関しては、日本使節を呼ぶどんな理由があるのか、わからない。しかしペテルブルグの政府がシベリアの権益を守るため、日本との間に緊密な関係を維持することに重要性を見いだすのは当然で、また頻繁にこの海域にロシア軍を現れるようにすべきだと考えるこの政府が、日本使節渡米の機会をとらえて、ペテルブルグにも立ち寄るよう要請したとしても、驚くことではない。」
さらにイギリスにも派遣されると見なしていたようだ。
「あまり言われていないが、日本使節はロンドンにも赴くようにとの同様の訓令を受けている。イギリス政府と江戸幕府との関係は、今日までわれわれと幕府との関係より、ずっと緊密な性格をもっているようには見えない。…イギリス政府が自ら日本使節の派遣を要請したかどうかは、わからない。」
(『絵入りロンドン・ニュース』1860年6月16日号) 当館蔵

5月に入ってすぐに、駐英大使から報告書(同前、1860年5月2日付、駐英大使から本省宛て報告書の写し)が届き、日本使節はヨーロッパに向かわず、帰国すること、イギリスは派遣を要請しておらず、それどころか使節受入はかえって費用もかかり迷惑だと考えていること、それよりもつぎのように貿易の発展を重視していることがわかった。
「駐日総領事[オールコック]の最近の報告によると、すくなくとも茶と生糸貿易を通じて2国間の関係は見通しの明るい発展的将来が期待されるとのことであるため、イギリス政府はあえてこの危険[日本使節の招聘]を冒そうとは思っていない。」


