|
ガス管の身元調査
写真2 ガス管は、ジョイント部分を中心に切断し、現在は横浜市が保管している(筆者撮影)

出土した2本のガス管は、裏山から校舎に向かって水平に並んでおり、うち1本は90度に折れ曲がって、地中へと消えていた【写真1】。
まずは、出土物の「身元確認」である。どこかに製造メーカーが手がかりを残していないかどうか。管と管をつなぐジョイント部分の土を落としてみると、アルファベットが出てきた。どうやらイニシャルのようだ。「RL & S」とある【写真2】。さらに裏側には「Y」。出土したジョイント部分には、いずれにも「RL&S」の陽刻が確認できた。このイニシャルこそが、ガス管の出自を明らかにする重要な情報なのである。
ここで、イニシャルの追求はいったん脇へおいて、「現場検証」にとりかかろう。もちろん、歴史的な現場検証である。
横浜瓦斯会社の事業主であり、現在も高島町という地名にその名を残している高島嘉右衛門が、この場所で施設の建設に取りかかるのは、明治4年のこと。翌5年9月29日には、記念すべき日本最初のガス灯が横浜の街に灯される。当時のガス会社の施設については、明治10年頃に伊勢山から撮影された【写真3】、および明治7年から11年にかけて測量された「横浜実測図」(図1)から、おおよその状況が把握できる。
写真3 明治10年ごろの横浜瓦斯局

写真中央に見えている円筒状のものがガスホルダー、すなわちガス溜である。そして、その右手に見える煙突をもった石造の建物が、ガス製造所である。製造所でつくられたガスは、背後のホルダーで蓄えられ、地中に敷設された管を通って市内へと供給されていた。地図でも確認できるが、敷地の前を流れる川に渡された「瓦斯橋」とは、その名のとおりガス管を対岸に渡すために架けられた橋なのである。
今回、ガス管が出土した区域は、ちょうどガス製造所とガスホルダーとのあいだの部分に位置する。2本の管のうち片方(写真右側)が、90度に折れ曲がって敷地の端へと向かっていることの意味を考えれば、この2本は、製造所でつくられたガスをホルダーへと運ぶための管(写真左側)と、ホルダーを出て市内へと向かっていく管ではないかと推察される。もちろん、管の前後が出土していないので、断定はできないのであるが。
図1 「横浜実測図」(明治14年刊行)
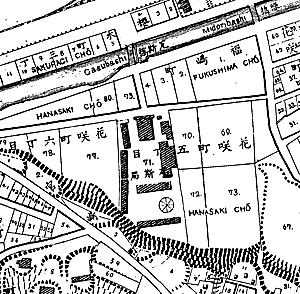
|

