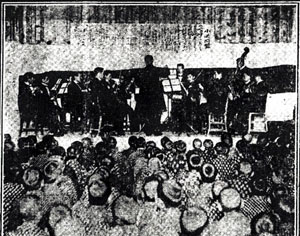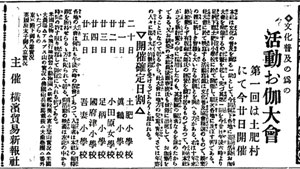HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第141号 > 資料よもやま話 『横浜貿易新報』の児童大会〈3〉
「開港のひろば」第141号
|
資料よもやま話
『横浜貿易新報』の児童大会
3 巡回児童大会
横浜貿易新報社は、「地方児童慰安啓発の為め」県下各地を巡回する児童大会を行なった。
最初は、1919年2月に藤沢・平塚・川崎・松田で、3月に横須賀で行なわれた。いずれも児童によるプログラムと、後藤の教訓絵話、奇術の余興が行なわれた。
第1回藤沢大会は9日に藤沢小学校で開催し、藤沢・鵠沼・明治各小学校から800名の児童が集まった。大会は、開会の辞、唱歌、朗読対話、談話など各校生徒が行ない、その間に後藤の教訓絵話をはさみ、最後に訓話、君が代の合唱で終った。
第2回平塚大会は12日に平塚尋常高等小学校で開催し、大野・中原・豊田・金田・須賀・馬入・平塚の7校1,300余名の児童と来賓・女子裁縫補習学校敬玉舎生徒ら200名を合せて1,500名に達する盛況だった。
第3回は15日に川崎小学校で開催し、川崎・大師河原・町田・田島・御幸各小学校生徒1,200名、来賓・学校職員・女子補習学校生徒100余名が観覧した。
第4回は19日町田町演芸館において、足柄上郡の21校1,200名の児童を集めて行なわれた。来賓等合せると1,400名に達した。
第5回横須賀大会は参加児童8校2,800名のため、3月2日豊島小学校で、男女別に午前・午後の2回に分けて行なわれた。女子の部は、開会の辞・朗読・独唱・唱歌・後藤の教訓絵話、途中に管弦楽を挟んで、君が代の合唱で終った。男子の部は、開会の辞・演説と管弦楽・後藤の教訓絵話、君が代の合唱で終った(図3)。
6月6日付紙面には、「市内の児童が各種の催しに接近する機会多きに比して、地方児童が此の機に接すること少なきを遺憾とし、本社は今回地方巡回部なるものを設けて、聊か地方児童の啓発を扶くることゝし、お伽話の大家後藤春樹氏を之が主任に聘し、今後各郡部に亘りて巡回口演を行なふことゝせり」(読点は筆者が補った)とある。この頃、後藤が入社したことがわかる。
後藤は6月4日に、鎌倉郡尋常戸塚小学校4・5・6年と高等1・2年生300名を集め、お伽講話を行なった。6月7日付の同紙によれば、後藤は小学校を訪ねて許可を得、いきなり講話を行なったようである。以後、小規模な講演を続け、この年、鎌倉郡・橘樹郡・高座郡・三浦郡・津久井郡・愛甲郡・足柄下郡・都筑郡でも「巡回お伽口演」を行なった。
1920年は、中郡・足柄下郡・都筑郡・高座郡・久良岐郡・津久井郡と巡回したが、このうち久良岐郡では、郡教育会の主催となっている。
1921年は、巡回3年目の第1回として、3月12日に愛甲郡連合児童大会に16校の児童3,000名が参加し、午前の部・午後の部に分けて、厚木小学校で行なわれた。後藤の教訓絵話を含む児童の演目は午前は21、午後は23で、これらに加え百面相の余興があった。
1922年は、5月20日から25日まで、「文化普及の為の活動お伽大会」を開催した。土肥・真鶴・小田原・足柄・国府津・吾妻小学校の六校でそれぞれ開催された。
5月20日付紙面(図4)によれば、公開する活動写真は、有坂錦太郎が経営する文化普及協会が精選したもので、娯楽のうちに新しい智識と大いなる教訓とを与える力があるという。それに加えて、後藤がお伽話をする。地方の児童だけでなく、青年、年配の人々にも歓迎されるであろう、と書かれている。開演時間が午後6時と遅めだが、それぞれ盛況のようであった。
このように、巡回児童大会は形を変えながら、1919年から1922年までの4年間続けられた。
おわりに
以上のように、横浜貿易新報社は1918年から、1家庭環境に恵まれない児童、2横浜市内の児童、3県下郡部の児童に対し、それぞれ児童大会を開催してきた。1は児童に慰安を与えるため、2と3については、娯楽の提供というよりは社会教育的な要素が強い。
大正時代には、子どもの関心や感動を中心に、自由で生き生きとした教育を目指そうとする運動がおこり、大正デモクラシーの風潮とともに広まった。横浜貿易新報社もその一端を担っていたのであろう。
(上田由美)